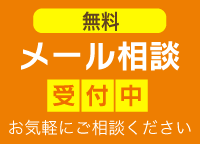白内障手術の失敗とは?|リスクを防ぐために知っておきたいこと【医師監修】
白内障手術の失敗とは?|リスクを防ぐために知っておきたいこと
はじめに
白内障手術は、日本国内で年間130万件以上行われており、非常にポピュラーな眼科手術です。しかし、「白内障手術が失敗することはあるの?」「どんなリスクがあるの?」といった不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、白内障手術における「失敗」とは何かを明確にし、どのようなリスクがあるのか、そしてそれを未然に防ぐために大切なポイントについて専門的に解説します。
白内障手術における「失敗」とは?
白内障手術が「失敗」することは、ほとんどありません。白内障手術も医療行為になりますので、必ず合併症などのリスクが存在しますが、合併症が起こったからといって手術が失敗したという訳ではありません。予測できる合併症であればリカバリーも可能ですし、時間の経過とともに消失していく合併症もあります。逆に、手術をしてみないと予測ができない合併症があることも事実です。白内障手術に限らず、手術という医療行為には必ずリスクが伴いますし、それをゼロにすることはできません。どの医療機関もリスクを回避するための努力は続けていると思います。合併症は、手術を行った場合に起こる可能性がある事象になりますので、起きてしまった場合には適切な対処をしてリカバリーすることになります。では、手術における「失敗」とは何を指すのでしょうか?それは、「故意または偶然の過失があった場合」「手術手技や手術器具などに問題があった場合」「薬剤の使用方法を間違えた場合」などが原因で重篤な合併症を招いてしまったり、得られるはずの結果が得られなかった場合を指します。
- 故意または偶然の過失によって重篤な合併症を起こした場合
- 滅菌していない手術器具を使いまわして感染症が起きた場合
- 手術手技に問題があって重篤な合併症を起こした場合
- 手術が原因で術前には認められなかった重篤な疾患を発症させた場合、
- 手術器具や薬品の使用方法を間違えて重篤な合併症を引き起こした場合
- 故意または偶然の過失によって得られるはずの結果が得られなかった場合
白内障手術で失明するケースは極めてまれです
近年、白内障手術が原因で失明したと言った報告を耳にしたことはありません。それだけ、白内障の手術手技が確立されてきたと言えるのでしょう。しかし、世界的にみると失明原因の第1位は白内障になります。これは、発展途上国などで、「十分な治療を受けられなかった」「治療を受けられる施設がない」「治療費を準備できない」「医療水準が低い」といた理由からです。日本では、白内障による失明率は3%と非常に低く、その原因は白内障を放置したことが主な原因です。
白内障手術で起こり得る合併症リスク
合併症といっても必ず起こる訳ではありませんので、過度に心配しすぎて手術が手遅れになる方が危険です。また、個々の目の状態や既往歴などによっても、起こり得る合併症に違いがありますので、リスクの説明内容も個々によって違いがあります。ただし、手術を受ける上でリスクについて知っておくことは重要だと思いますので、主な合併症についてご紹介していきます。白内障手術では以下のようなリスクが考えられます。
破嚢
水晶体を包んでいる水晶体嚢が破れてしまう手術中に起こりやすい合併症です。前嚢切開や水晶体分割の工程で起こりやすく、状態によってはレンズを挿入できなくなることもあります。
後嚢破損
水晶体を包む膜の後ろ側が破れてしまう手術中に起こりやすい合併症です。水晶体分割の工程で起こる可能性があり、水晶体や砕いた水晶体の破片が目の中に落下してしまうケースもあります。大きな破片が落下した場合は、放置すると炎症を起こすこともありますので、硝子体手術で落下した水晶体を取り除く必要があります。小さい破片の場合は、自然に吸収されるのを待ちます。
チン小帯断裂
水晶体を支える繊維が切れてしまう症状です。加齢によってチン小帯が弱っていることがありますので、わずかな力でチン小帯が断裂してしまうことがあります。手術手技が原因で起こることは稀で、最初からチン小帯が弱っていることで起こるケースが大半です。慎重に手術を継続できる場合もありますが、断裂が広範囲に広がってしまう場合は、落下を防ぐために水晶体を全適します。レンズを挿入することができなくなるため、逢着固定や強膜固定といった特殊な方法でレンズを固定します。
水晶体落下
破損した膜から水晶体やその破片が眼内に落下してしまう事象です。小さい破片の場合は、自然に吸収されるのを待ちますが、大きい破片の場合は放置すると炎症が起こって眼圧が上昇してしまうため、硝子体手術を行って破片を取り除く必要があります。
眼内感染(眼内炎)
目は栄養が豊富な器官になるため、細菌が入ると繁殖しやすい環境にあります。感染症が起こることは非常に稀ですが、失明につながる重大な合併症の一つでもありますので、最も注意すべき合併症の一つといえるでしょう。
後発白内障
手術後に、もともと水晶体を包んでいた水晶体嚢が濁る症状を指します。後発白内障は、白内障手術を受けたすべての方に見られる症状で、残った水晶体上皮細胞が増殖することが原因で起こります。視力に影響するケースは全体の20%ほどになりますが、レーザー治療が可能です。
ハロー・グレア(夜間光視症)
白内障手術後にハロー・グレアという症状が出ることがあります。これは、夜間に街灯などの強い光源を見た時に、光が散乱したり、光源の周囲に輪のようなものが見える症状になります。ハロー・グレアは、手術を受けていなくても見える現象になりますが、何十年も慣れ親しんできた見え方になるため、違和感を覚える人は少ないでしょう。ただ、白内障手術後は、新しい見え方に変わりまので、ハロー・グレアが気になるというケースもあります。また、瞳孔の大きさとレンズの大きさにも関係している場合もありますは、通常は時間の経過とともに解消していきます。
レンズの度数ズレ
眼内レンズをオーダーする際は、検査データをもとにレンズの度数を計算しますが、手術後に度数が合っていないというケースがあります。過去にレーシックを受けたという方は、レンズの計算方法が特殊になるので、度数ズレのリスクが若干高くなります。そのため、過去にレーシックを受けている場合、白内障手術を断られることもあるようです。当院は、レーシック手術にも対応していますので、過去にレーシックを受けられている方の白内障手術も歓迎しています。
合併症のリスクを低減するために
白内障手術を行っている施設では、合併症のリスクを低減するために様々な取り組みを行っていることでしょう。当院では、外科的手術にも対応できるクリールームを完備しています。また、使い捨て出来るディスポーザブルの医材を多く採用して感染症対策に取り組んでいます。使用する器具の洗浄・滅菌の徹底、清潔と不潔の区別に関する指導を徹底するなど、スタッフ全員の取り組みによって、これまで感染症が起こったことはありません。
レーザー白内障手術でリスクを軽減
冨田実アイクリニック銀座では、白内障手術の安全性と精度をさらに高めるため、レーザー白内障手術システム「Perfect Z-CATARACT System」を導入しています。
前嚢切開をレーザーで行うことで術中の合併症も軽減することができますし、正確な前嚢切開により、眼内レンズの安定性が向上します。
レーザーによる水晶体分割は、眼内での作業を少なくすることができますので、合併症のリスク抑制と手術によるダメージ軽減を実現しています。
フェムトセカンドレーザーに搭載されたOCT機能により、執刀中に水晶体の断面画像をリアルタイムで確認可能。個々の目の状態に合わせて、分割する深さを設定することもできますので、手術を安全に行うために欠かせない機能と言えるでしょう。
これらのテクノロジーによって、マニュアル手術で起こり得る合併症のリスクを最小限に抑え、常に安定した手術結果を実現しています。
まとめ
白内障手術は、手術手技も確立されて安全性の高い手術になります。決してリスクがゼロというわけではありませんが、手術の成功率を高めるためには、設備の整った施設で、経験豊富な眼科専門医による診察と手術を受けることが大切です。
冨田実アイクリニック銀座では、フェムトセカンドレーザーなどの先進技術を導入し、患者様一人ひとりの眼の状態に合わせた安全性の高い白内障手術を提供しています。手術への不安や疑問がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
監修者

最新の記事
- 2025年10月5日コラム白内障手術を受けるまでの流れ|来院から帰宅までの体験ガイド【医師監修】
- 2025年10月4日コラム白内障の原因は加齢だけじゃない?|白内障の様々な原因について解説【医師監修】
- 2025年10月3日コラム初期の白内障に気づくには?|見逃しやすい症状とセルフチェック法【医師監修】
- 2025年10月2日コラム白内障の進行を遅らせることはできる?|予防と生活習慣の関係【医師監修】
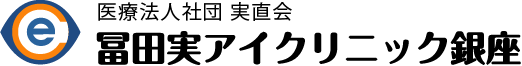
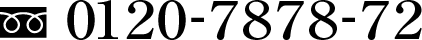 お問い合わせ受付時間 9:30〜19:00
お問い合わせ受付時間 9:30〜19:00